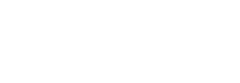眠れないまま朝になったときどうする?睡眠不足で仕事や学校を乗り切る方法

眠れないまま朝になった経験がある人は多いでしょう。疲労が蓄積したままでは、日中の活動への不安や、次の夜も眠れないのではないかという心配が募ってしまいがちです。
この記事では、眠れないまま朝になった原因や、1日を乗り切る対処法やリフレッシュ法などを解説します。
眠れないまま朝になってしまったときに考えられる原因
眠れないまま朝になった原因はさまざまです。主な原因を紹介するので、心あたりがないか考えてみましょう。
生活習慣・環境の乱れ
不規則な生活リズムや運動不足、食事時間の乱れなどは、質のよい睡眠を妨げます。寝室の温度や湿度、明るさなどが適切に整えられていない場合にも、睡眠の質が悪くなる可能性があります。
心理的なストレス
仕事や人間関係からのストレス、不安や緊張などの精神的な負担も、睡眠を妨げる要因となります。強いストレスを感じると交感神経が刺激され、その結果、眠れなくなることがあります。たとえ眠れてもストレスがあると深い睡眠が阻害され、眠りの質が低下しやすいことも分かっています。
カフェイン・アルコールの摂り過ぎ
カフェインを摂りすぎや摂る時間帯によっては覚醒作用により睡眠の質が低下する可能性があります。個人差によりますが夕方以降は、カフェインを控えることをおすすめします。また、アルコールは一時的な睡眠導入効果はあるものの、過度に摂取すると眠りが浅くなり、睡眠の質を著しく低下させます。
女性ホルモンに由来する不調
月経周期に伴うホルモンバランスの変化は、女性の睡眠に影響を与える場合があります。特に生理中は、ストレス耐性を高めるホルモンの分泌が減少し、結果的に不眠になりやすい傾向が見られます。
眠れないまま朝になってしまったときに1日を乗り切る方法
1日を乗り切るために日中の生活でリカバリーをしてみませんか?1日を乗り切るために日中の生活でリカバリーをしてみませんか?以下の方法で、体調管理と生活リズムの回復を図りましょう。
太陽の光を浴びる
朝の光を浴びると、乱れてしまった体内時計が整えられます。朝の光を感知した体は、約14時間後に自然な眠気を感じるようになるとされています。
たとえ寝不足でも、あえて起床し、朝日を浴びるようにしましょう。朝寝をして光を浴びる時間が遅れると、体内時計が乱れやすく、その日の睡眠にも影響を及ぼす可能性があります。
運動やストレッチをする
朝の軽い運動は体を目覚めさせます。ウォーキングや散歩程度の軽い運動でも充分な効果が期待できます。ストレッチによる血行促進は、心身のリフレッシュに効果的です。
また、日中の運動によってもたらされる適度な身体的疲労や、寝る前の軽いストレッチは夜の良質な睡眠を促します。
エネルギーを産み出す栄養を摂る
睡眠不足の体を労るため、また体のリズムを整えるためにも朝食でしっかりとした栄養補給を行いましょう。特にアミノ酸の一種であるトリプトファンは、睡眠の質を左右するホルモンの生成に関わる重要な栄養素です。トリプトファンは青魚や乳製品などに多く含まれています。
また、疲労回復や集中力維持に向け、ビタミンの摂取もおすすめします。いつもの朝食のメニューに果物や野菜を取り入れ、バランスのよい食事を心がけましょう。
カフェインを摂取する
コーヒーや緑茶などに含まれるカフェインには、覚醒作用があります。しかし、効果が切れたと感じても、安易に飲み続けないようにしましょう。カフェインの過剰摂取は不眠や胃腸の不調を引き起こすだけではなく、精神を不安定にさせる可能性があります。
また、空腹時のカフェイン摂取は胃への負担が大きいため、朝食を摂ってからコーヒーなどを飲むようにしてください。程度な量であれば、眠気を解消したり集中力をあげたりすることに役立ちます。
15時までに短時間の仮眠を取る
疲労や眠気を感じながら作業を続けると、作業効率が低下しミスも増えやすくなります。休んだ方がよさそうと感じたら、15〜20分程度の短時間の仮眠を15時までに取るようにしましょう。寝不足のせいでいつもより午後の眠気や疲れが強くなります。仮眠によって前日の不足した睡眠を補充するので疲れが和らぎ、頭もスッキリするでしょう。
なお、15時以降に長い仮眠をとってしまうと、その日の夜の睡眠に影響してしまうため仮眠をとる時間帯と長さには気をつけてください。また、仮眠の前にコーヒーなどのカフェインを摂取すると覚醒作用で起きやすくなります。
覚醒効果の高いツボを押す
ツボを刺激することで、血行促進や疲労感の軽減が期待できるとされています。たとえば、膝下の「足三里」には覚醒効果があるとされています。
また、手首の「神門」にはリラックス効果があるとされているので、就寝前にリラックスしたいときに押してみるとよいでしょう。このように、ツボを活用することで、心身のコンディションを整えやすくなります。
眠れないまま朝になってしまった時の注意点
眠れないまま朝になったときは、事故や体調悪化のリスクが高まります。安全と健康のために、以下の点に注意を払いましょう。
眠れないまま朝になってしまったら車の運転は控える
睡眠不足の状態での運転は、飲酒運転と同程度に危険な行為とされています。疲労と眠気により判断力が著しく低下すると、重大な事故につながるリスクが高まります。たとえ短距離であっても、眠気を感じる場合は運転を避けるべきです。
特に、長距離運転が予定されている場合は、公共交通機関の利用やドライバーの交代を検討しましょう。
体調によっては仕事や学校を休むことも検討
質のよい睡眠は、心身の健康を維持するために欠かせません。以下のような予定があれば、仕事や学校を休むことも検討しましょう。
- 危険を伴う機械操作や高所での作業
- 細心の注意が必要な業務
- 体育など激しい運動が予想される授業
睡眠不足状態で無理に活動を続けると、作業効率の低下だけではなく、重大なミスや事故のリスクも高まります。
眠れないまま朝を迎えないために日頃からできる生活習慣
「眠れないまま朝になった」を避けるための対策を紹介します。できるところから少しずつ、生活習慣を見直してみましょう。
寝る前の行動をルーティン化する
就寝前にリラックスする習慣を取り入れましょう。たとえば、以下の習慣がおすすめです。
- 腹式呼吸
- ストレッチ
- アロマテラピー
- 読書
- 音楽鑑賞
リラックスすると副交感神経が優位になり、自然な眠気がもたらされます。反対に、スマートフォンやパソコンは脳を覚醒させてしまうため、就寝前は使用を控えましょう。
睡眠環境を見直してみる
温度や湿度、照明、静けさ、パジャマ、寝具などにこだわって睡眠環境を見直しましょう。厚生労働省によると、寝床内の温度は33℃前後、湿度は50%程度が理想とされています。眠気を促すためには、照明を落とした静かな環境を整えることも大切です。
さらに、体を締めつけない通気性のよいパジャマを選びましょう。特に綿やシルクなどの天然素材は触り心地がよく、快適に眠れると考えられます。
決まった時間に布団から出る
体内時計を整えるには、平日・休日を問わず一定の時間に起床しましょう。
たとえば、休日に寝だめをしようとして起床時間が大きくずれると、体内時計が混乱し、夜の睡眠に影響が出てしまいます。
多少眠気が残っていても、決まった時間に起きて朝日を浴びる習慣を続けることで、健全な睡眠サイクルを維持できます。
寝る数時間前の入浴で身体を温める
就寝1~2時間前の入浴は、質のよい睡眠を促す効果があります。ぬるめの温度でゆっくり体を温めておくと、温まった体温が低下する過程で自然な眠気が誘発されるためです。入浴後は急激な体温低下を防ぐため、パジャマの着用やドライヤーでの髪の乾燥を心がけましょう。
なお、就寝前に熱い湯船に浸かると、交感神経が優位になって眠れなくなる恐れがあるため注意が必要です。
リラックスできる時間を作る
仕事や勉強、家事などに追われる日々でも、就寝前の時間は意識的にリラックスモードに切り替えましょう。趣味の時間を確保したり、瞑想で心を落ち着かせたりすると、精神的な緊張を解きほぐせます。
また、睡眠時間にこだわりすぎず「目をつむって横になっているだけでも少しは体を休められる」などと柔軟な考えを持つことも大切です。眠れない不安や焦りは、かえって睡眠を妨げる場合があるためです。
眠れないまま朝になる日が続く場合は治療が必要な場合も
何らかの病気によって眠りに影響が出ている可能性もあります。以下のような症状が続く場合は、専門医への相談をおすすめします。
自律神経失調症
自律神経失調症とは、体を活性化させる交感神経と、リラックスを促す副交感神経のバランスが崩れた状態のことです。自律神経失調症の原因には、過剰なストレスや不規則な生活習慣、ホルモンバランスの乱れなどが挙げられます。睡眠障害は、自律神経失調症の代表的な症状のひとつです。
不眠障害
寝つきの悪さ(入眠困難)、夜間の頻繁な目覚め(中途覚醒)、早朝の目覚め(早朝覚醒)、充分な睡眠時間があっても疲労感が残る状態(熟眠障害)などが、不眠障害の特徴です。症状が長期間継続する場合は、日常生活に重大な支障をきたす可能性があります。
睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群になると、睡眠中に呼吸が停止あるいは低下し、酸素の供給が妨げられ、質のよい睡眠が得られない状態となります。本人は自覚症状に乏しいことが多く、家族からの「大きないびき」の指摘や、日中の過度な眠気が診断の手がかりとなります。
うつ病
不眠症状は、うつ病患者の大多数に見られる主要な症状です。うつ病により不眠となる場合もあれば、不眠がうつ病の引き金となる場合もあります。食欲低下や興味・関心の喪失といった症状を感じている場合は、うつ病の可能性が考えられます。該当する場合は早めに専門医へ相談することをおすすめします。
概日リズム睡眠障害
概日リズム睡眠障害は、体内時計の乱れにより、睡眠と覚醒のリズムが崩れ、社会生活に支障をきたすようになった状態です。概日リズム睡眠障害は「怠惰なだけ」と誤解されやすく、周囲の理解が得られにくい結果、うつ病を発症するリスクもあります。専門家による適切な治療と生活指導が必要です。
眠れないまま朝になってしまったら無理はしない
眠れないまま朝になったときは、眠気覚ましやリフレッシュにつながる行動により、1日を乗り切れる可能性があります。ただし、無理はせず、疲労や眠気が深刻な場合は休む判断も必要です。眠れなかった原因を探り、スムーズに眠りにつけるように生活習慣や睡眠環境を見直してみましょう。
LOFTY(ロフテー)は、エアウィーヴグループの枕ブランドで、2期連続でオリンピック公式寝具スポンサーに選ばれています。枕の計測販売という画期的な方法を創り上げたLOFTYは、お客さま一人ひとりに最適な枕を提供してきました。全国の有名百貨店に実店舗を展開中で、累計350万個以上の販売実績があります。快適な睡眠環境を整えるためにも、ぜひLOFTYの枕をご検討ください。