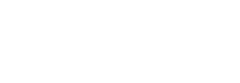目覚めを良くする方法!目覚めが悪くなる原因とスッキリ起きるための習慣

良質な睡眠と爽やかな目覚めは、日々の生活の質を左右する要因になります。年齢を重ねるにつれて、目覚めが悪くなると感じている方も多いのではないでしょうか。本記事では、目覚めが悪くなる原因と、スッキリ起きるための具体的な方法について詳しく解説いたします。
目覚めが悪くなるおもな原因
朝のだるさや眠気を解消するためには、まずその原因を理解することが大切です。まず目覚めが悪くなるおもな原因について解説します。
〇 睡眠の質の低下
加齢とともに、睡眠の質は徐々に低下していきます。深い睡眠の時間が減少し、浅い睡眠が増えることで、朝の目覚めがスッキリしなくなります。睡眠の質が低下すると、長時間眠っても休息が得られません。
具体的には、中途覚醒の増加や睡眠サイクルの乱れが睡眠の質の低下と関連しています。
〇 自分に合っていない寝具の使用
心地よい睡眠を促すためには、自分に合った寝具を使いましょう。枕やマットレスが体型に合っていないと、睡眠中に腰や肩、首などに負担がかかり、身体が痛くなってしまいます。
さらに筋肉の緊張が生じ、途中で目が覚めることもあるでしょう。これはレム睡眠とノンレム睡眠の周期が乱れる原因となり、質の高い睡眠が得られず、朝の目覚めも悪くなってしまいます。
〇 過剰なストレスの蓄積
ストレスは交感神経を優位にし、心拍数を高め、心の高揚や緊張を招きます。その結果、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりするでしょう。仕事や人間関係など日常生活におけるストレスが続くと、交感神経の働きが活発になり、心身が常に緊張した状態になります。
ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌も増え、さらに交感神経を刺激してしまいます。
〇 いびきや睡眠時無呼吸症候群の影響
いびきは単なる音の問題ではなく、睡眠の質を大きく低下させます。特に睡眠時無呼吸症候群では、寝ている間に何度も呼吸が止まり、脳や身体が酸欠状態になります。その結果、深い睡眠が得られず、充分な時間眠っても疲れが取れないという状態に陥るでしょう。
日中の強い眠気や集中力の低下も、この症状の特徴です。
関連記事:枕の高さといびきの関係とは?睡眠の質を上げる枕選びのコツとおすすめ枕を紹介!
関連記事:いびきの対処法とは?
〇 就寝前のアルコール摂取
眠れないからとお酒を飲む習慣は、実は逆効果です。アルコールには入眠を促す効果がありますが、睡眠の質を低下させてしまいます。厚生労働省が推進する国民健康づくり運動「健康日本21」によると、適度な飲酒量は1日平均純アルコール20g程度とされています。
これを超える量を習慣的に飲んでいると、不眠状態が続き、翌朝の目覚めが悪くなってしまうでしょう。
〇 夜遅い時間の食事
食後、胃腸の働きが落ち着くまでには約2〜3時間かかります。寝る直前に食事をすると、消化活動のために内臓と脳が覚醒状態になり、寝つきが悪くなったり、夜中に目が覚めたりするでしょう。
また、消化に使われるエネルギーは、本来なら古くなった細胞の修復や新陳代謝の活性化に使われるものです。夜遅い食事は睡眠を妨げるだけでなく、身体の疲労回復も阻害してしまいます。
〇 多忙からくる不安感
仕事やプライベートで忙しい毎日を送っていると、「今日やり残したこと」「明日やるべきこと」などが頭に浮かび、なかなか眠れなくなることがあります。これは多忙によって頭の中が整理できておらず、交感神経が働いてしまうことで起こる現象です。
予定が詰まっていると眠りが浅くなったり、目覚めが悪くなったりするのは、このような不安感が原因となっています。
目覚めをよくする方法:「夜」の習慣
良い目覚めのためには、質の高い睡眠が欠かせません。夜の習慣を見直すことで、睡眠の質を高め、朝のスッキリとした目覚めにつなげることができます。
〇 自分の身体に合った寝具を使用する
質の高い睡眠には、身体や寝姿勢に合った寝具を選びましょう。特に枕は首や肩の負担を和らげる役割を果たします。また、寝返りには、熱や湿気を放出し、血液循環を良くする効果があるので寝返りのしやすさも大切です。
横向きになったとき、腰から首にかけて背骨のラインがまっすぐになる枕がおすすめです。自分に合った寝具で眠ることで、睡眠の質が向上し、朝の目覚めも良くなります。
〇 就寝前に入浴する
睡眠の質を高めるためには、就寝の2~3時間前に入浴することが効果的です。38〜40度程度のぬるめのお湯に5~30分浸かると、一時的に体温が上昇し、その後緩やかに下がります。この体温の変化が自然な眠気を促します。
熱すぎるお湯は交感神経を刺激して脳が興奮状態になるため避け、ぬるめのお湯でゆっくりと体を温めることがポイントです。
〇 夕食は就寝の3時間前までにとる
消化活動は睡眠を妨げる要因となるため、夕食は就寝の2〜3時間前までに済ませるようにしましょう。寝る直前に食事をすると、消化活動により内臓と脳が覚醒状態になり、寝つきが悪くなったり、夜中に目が覚めたりすることがあります。
特に脂肪分の多い肉類や揚げ物は消化に時間がかかるため、夕食では控えめにするのがおすすめです。
〇 就寝時は部屋の明かりを暗くする
睡眠を促進するホルモンであるメラトニンは、明るい環境で分泌が抑制されます。就寝前には照明を少し落として薄暗い環境を作ることで、自然な眠気を感じやすくなります。就寝前1時間は、やや暗く暖色の間接照明やスタンドの照明にすることをおすすめします。
暗闇が苦手な人は間接照明を使用し、リラックスできる程度の明るさを保ちながらメラトニンの分泌を促しましょう。
〇 音楽を聴きリラックスする
ストレスを抱えたまま寝ると、睡眠で疲れが取れず、朝の目覚めが悪くなる可能性があります。就寝前にヒーリングミュージックなどのリラックスできる音楽を聴くことで、副交感神経の働きが高まり、心身をリラックスさせることができるでしょう。
心地よいと感じる音楽は脳のα波を引き出し、寝つきやすくし睡眠の質を高める効果が期待できます。
関連記事:「寝る前の音楽」記事
目覚めをよくする方法:「朝」の習慣
目覚めを良くするためには、朝の過ごし方も大切です。ここでは、朝に実践したい習慣について紹介します。
〇 朝日を浴びる
朝起きたらすぐにカーテンを開け、太陽の光を浴びましょう。朝の日光は体内時計をリセットし、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制します。同時に、セロトニンという覚醒を促すホルモンの分泌が活発になり、脳と身体が活動モードに切り替わります。
朝の日光浴は気分改善や眠気の解消にも効果的です。そして約14〜16時間後に自然な眠気が訪れるようになるでしょう。
〇 起床後すぐ水分補給する
人は睡眠中にコップ1杯分(約200ml)もの汗をかくため、起床時の水分補給は忘れないようにしましょう。朝起きたら、常温の水や白湯をコップ1杯(250〜500ml程度)飲むことをおすすめします。
これにより、夜間に失われた水分を補給できるだけでなく、脳への血流が促進され、より覚醒した状態になります。
〇 身体を目覚めさせる軽い運動を行う
朝のストレッチや軽い運動は、夜間の睡眠で固まった体をほぐし、一日を健やかにスタートさせるのに役立ちます。10分程度のヨガ、ウォーキングなど、自分が楽しめるものを選ぶことが継続のコツです。
朝の運動は自律神経のバランスを整え、血流を促進し脳と身体を活動モードにします。
〇 朝食を欠かさない
朝食をとることで、脳にエネルギーが補給され、体温が上がり、体内時計がリセットされます。これにより、身体は休眠モードから活動モードへと切り替わります。朝食は主食・主菜・副菜とバランスよくとりましょう。
特にタンパク質(卵やヨーグルト)、穀物(持続的なエネルギー源)、果物や野菜(ビタミンやミネラル)を含む食事がおすすめです。
スッキリ起きるために寝る前に避けるべきこと
質の高い睡眠を得るためには、就寝前の行動にも注意が必要です。ここでは、寝る前に避けるべき習慣について解説します。
〇 カフェインの摂取
デトロイトのヘンリーフォード病院での研究では、寝る6時間前のカフェイン摂取でも睡眠に影響があることが示されています。カフェインの作用は個人差によりますがコーヒーやお茶などカフェインを含む飲み物は、夕方以降控えるようにしましょう。
カフェインが体内に残っていると、脳が興奮状態になって寝つきが悪くなるほか、眠りが浅くなり、朝の目覚めにも影響を与えます。
〇 パソコンやスマートフォンの使用
就寝前のパソコンやスマートフォンの使用は、質の高い睡眠の大敵です。これらの機器から発せられるブルーライトは、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑え、寝つきを悪くします。
就寝の2時間前からはデジタル機器の使用を控え、代わりに読書やストレッチなど、リラックスできる活動に時間を使いましょう。
まとめ
目覚めを良くするためには、睡眠の質を高めることが大切です。目覚めが悪くなる原因は、睡眠の質の低下、自分に合わない寝具の使用、過剰なストレス、いびきや睡眠時無呼吸症候群、就寝前のアルコール摂取、夜遅い時間の食事、多忙からくる不安感などが挙げられます。これらの問題を解決するためには、夜と朝の習慣を見直すことが効果的です。
特に寝具選びは睡眠の質に直結します。ロフテー(LOFTY)の枕は、独自の5または9分割構造で首や肩への負担を和らげ、安定した寝姿勢をサポートします。下記リンク内の「枕の選び方」より、お悩み毎におすすめの枕を提案しております。ぜひ一度ご覧ください。