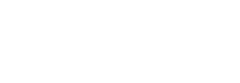眠れない夜に押すツボ13選|眠くなる・安眠できるツボ【頭部・耳・手・足】を解説

全身にあるツボのなかには、安眠につながるものもあります。
本記事では、寝つきの悪さや睡眠不足に悩む人に向けて、安眠につながるツボを耳・手・足などの部位ごとに紹介します。
ツボ押しの効果を高めるポイントや、ツボ押しと組み合わせたいおすすめの快眠法も解説するので、ぜひ参考にしてください。
なぜツボを押すと不眠を緩和できるの?
そもそも、なぜ快眠のツボを押すと寝つきがよくなり、睡眠不足の解消につながるのでしょうか?
ツボ押しは東洋医学に基づく療法
「西洋医学」では薬や手術などで身体の悪い部分に直接的にアプローチするのに対し、「東洋医学」では自然治癒力に着目し、身体全体のバランスを整えることを目的とします。
ツボとは東洋医学の「気」の概念に基づくもので、正式名称は「経穴(けいけつ)」です。経穴は気の通り道における出入り口を指し、刺激するとそれぞれに対応する臓器や部位に作用して、身体を整えられると考えられています。ツボ押しの効用はWHO(世界保健機構)にも認められており、全部で361個のツボが定められています。
快眠のツボを押すと眠くなる理由
快眠のツボを押すと、眠れない原因にアプローチできるため、眠くなりやすくなります。
快眠のツボを押すと血流が促進され、身体の冷えや筋肉のこわばりの改善につながるとされています。また、ツボ押しは呼吸のリズムに合わせて行うため、副交感神経が優位になり身体をリラックスモードへ導きます。
手足の冷えや心身の緊張などにより眠れない場合は、快眠のツボを押すことでスムーズに入眠しやすくなるでしょう。
眠くなるツボ【頭部~耳】
ここからは、快眠のツボの位置や効果について解説します。
まずは、頭部(頭〜耳)にあるツボから紹介します。頭〜耳にある眠くなるツボの代表例は、以下の5つです。
百会(ひゃくえ)
百会は、頭頂部の真ん中あたりの、少しへこんだところにあるツボです。副交感神経を優位にする働きを期待でき、心身をリラックスモードへ導いてくれるとされています。
身体の冷えが気になるときや、寝不足で頭がぼんやりするときにもおすすめです。
完骨(かんこつ)
完骨は、耳の後ろの出っ張った骨の、斜め後ろにあるツボです。耳たぶの裏のくぼみの延長線上に位置し、押すと少しへこんでいることが分かります。自律神経にアプローチできるほか、肩こりや頭痛の緩和にもつながるとされています。
安眠(あんみん)
安眠は、耳の後ろの出っ張った骨から、指1本程度下にあるツボです。副交感神経を優位にするとされており、スムーズな入眠につながります。
首や肩の筋肉のこわばりを和らげる効果もあると考えられています。
囟会(しんえ)
囟会は、おでこの上部にあるツボです。頭頂部の真ん中にある百会から、親指3本分程度おでこ側にずれた位置にあります。心身をリラックスモードへ導いてくれるほか、頭痛や鼻詰まりなどにも効果を期待できるとされています。
迎香(げいこう)
迎香は、左右の小鼻のわきにあるツボです。「香りを迎える」という由来のとおり、鼻の通りを良くする効果を期待できるとされています。鼻炎や花粉症などで、鼻詰まりが気になって眠れない人におすすめです。
眠くなるツボ【手】
手には数多くのツボが集まっており、安眠につながるツボもさまざまあります。横になった状態でもツボ押しがしやすいので、布団に入ったけれど眠れないというときにもおすすめです。
神門(しんもん)
神門は、手の内側の小指側、手首のしわの上にあるツボです。精神を安定させる効果があると考えられており、イライラや不安などで眠れないときに適しています。また、ストレスが原因の動機・息切れや小指から手首にかけての痛み、便秘などにも効果があるとされています。
労宮(ろうきゅう)
労宮は、手のひらの上部にあるツボです。手を軽く握ったときに、ちょうど人差し指と中指の先端の真ん中に位置する場所にあります。自律神経を整えて、全身の緊張を和らげる効果があると考えられています。
井穴(せいけつ)
井穴は、手の指の爪の付け根にあるツボです。爪の生え際から2mm程度下がったところの両端、左右の各指に2つずつあり、副交感神経の働きを優位にすると考えられています。ただし、薬指だけは反対に覚醒効果があるとされているので、眠れないときは避けましょう。
内関(ないかん)
内関は、手首の内側にあるツボです。手首を内側に曲げたときにできる太いシワから、親指2本分程度下に位置し、押すとピリピリと刺激を感じる点が特徴です。自律神経を整えて、安らかな眠りへと導いてくれるとされています。
合谷(ごうこく)
合谷は、手の甲側の、親指と人差し指の分かれ目から、やや人差し指側にあるツボです。押したときに、少し痛みを感じる場所を探ってみましょう。自律神経を整えるだけでなく、頭痛や肩こり、眼精疲労などさまざまな症状へのアプローチにおすすめです。
眠くなるツボ【その他の部位】
快眠につながるツボは、頭や手以外にもさまざまあります。ここからは足やお腹など、そのほかの部位の安眠のツボを紹介します。
失眠(しつみん)
失眠は、かかとの真ん中あたりにあるツボです。神経の昂ぶりを抑えるとされており、下半身の冷えの緩和にもつながると考えられています。かかとの皮膚はかたいので、少し強めに押すとよいでしょう。
関元(かんげん)・丹田(たんでん)
関元は、おへそから3〜5cm程度下にあるツボです。丹田とも呼ばれるこのツボには、全身の気が集まると考えられています。交感神経の働きを抑えてリラックスモードへ導いてくれるだけでなく、腹痛や腰痛の緩和にも効果を期待できます。
膻中(だんちゅう)
膻中は、胸の真ん中あたりにあるツボです。左右の乳頭を線で結んだときに、ちょうど中間にくる場所に位置します。自律神経を整えるとされており、不安やストレスの緩和に効果を期待できます。
ツボ押し効果を上げるための3つのポイント
ツボ押しの効果を高めるためには、正しい押し方を知ることが大切です。次の3つのポイントを押さえて、ツボ押しの快眠効果を高めましょう。
呼吸に合わせてツボを押す
ツボ押しは、呼吸のリズムに合わせて行います。息を吐きながらツボを押し、息を吸うときに力を抜くという動作を繰り返しましょう。深呼吸をしながらゆっくりとツボを押し、少しずつ力を抜くことがポイントです。
痛気持ちいい強さで押す
ツボ押しは力を入れるほど効果が高まるものではなく、かえって気持ちが昂って寝つきが悪くなる可能性があります。ツボ押しの力加減は、痛気持ちいいくらいの強さがベストです。正確な場所にこだわりすぎず、気持ちいいポイントを押しましょう。
力加減がよく分からない場合は、ツボのまわりを温めるだけでも効果を期待できます。
就寝前のリラックスタイムに行う
ツボ押しは、リラックスした状態で行うことが大切です。入浴や歯磨きなどを済ませ、あとはもう寝るだけという状態で、睡眠の30分〜1時間前に行うとよいでしょう。
部屋の照明を暗くするなどして、リラックスできる環境を整えることもおすすめです。反対に、食後1時間以内や飲酒後、テレビやスマートフォンなどを見ながらのツボ押しは避けましょう。
ツボ押しと組み合わせたい眠くなる方法
寝つきをよくする方法は、ツボ押し以外にもさまざまあります。複数の方法を組み合わせることで、快眠効果をより一層高めることも可能です。
寝室の環境を整える
寝室の温度や湿度が快適でないと寝つきが悪くなり、睡眠の質が低下する原因になります。エアコンや暖房器具などを活用して、布団に入る前に寝室の環境を整えておきましょう。
また、照明の明るさも重要なポイントです。真っ暗だとかえって眠れないという人は、安心して眠れる程度に暗さを調整しましょう。
夜はパソコンやスマートフォンの使用を控える
パソコンやスマートフォンの液晶から発せられる光(ブルーライト)には、覚醒作用があるとされています。寝る直前までSNSや動画を楽しんでいると、脳が覚醒して寝つきが悪くなる可能性があるので注意が必要です。
夜はパソコンやスマートフォンの使用はなるべく控え、どうしても必要な場合はブルーライトをカットする夜間モードなどを活用しましょう。
自分に合う枕を使う
自分に合わない枕を使用していると、肩や首などに負担がかかり寝つきが悪くなる原因にもなります。
枕にはさまざまな形状のものがあり、高さやかたさなどもさまざまあります。頭をのせたときに、頭と首をしっかり支えてくれて、呼吸がしやすい枕がおすすめです。
自分の身体や好みに合わせた枕を選んで、スムーズに眠れる環境を整えましょう。
▼こちらの記事では、さまざまな条件で枕を選ぶ方法を解説しているので、ぜひ参考にしてください。
眠くなるツボを押して快眠を手に入れよう
寝つきが悪くて眠れないときは、手軽に実践できるツボ押しがおすすめです。深呼吸をしながらツボを押し、力を抜く動作を繰り返すと、心身がリラックスして眠りやすくなります。
寝つきの悪さにお悩みの人には、枕の買い替えも検討してみましょう。創業97年の歴史を誇る枕ブランドの「LOFTY」は、オリンピック公式寝具スポンサーに2期連続で認定されています。全国の百貨店に製品を販売し、累計販売個数は350万個を突破。こだわり抜いた高品質の枕で、安らかな入眠をサポートします。