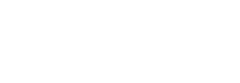眠くないのにあくびが止まらない?あくびが出る原因や対処法を解説

あくびは寝起きや睡眠不足のときなど、眠いときに出ることが多い傾向があります。しかし、なかには眠くないのにあくびが止まらず、職場や外出先などで困った経験のある人も多いでしょう。
本記事では、眠くないのにあくびが出るときに考えられる原因や、対処法について解説します。
目次
あくびが出る原因は解明されていない
あくびは起床時や就寝前に出ることが多いため、睡眠と密接な関係があると考えられています。しかし、実は、あくびが出る原因ははっきりとは解明されていません。
脳の視床下部にある室傍核(しつぼうかく)という場所から指令が出ることで引き起こされるという説が有力ですが、まだまだ不明な点が多く、現在も研究が進められています。
眠くないのにあくびが出るときに考えられる原因とは?
「眠くないときのあくび」は「眠いときのあくび」と区別して、「生あくび」と呼ばれることがあります。眠いときのあくびと同様、生あくびの原因もはっきりとしたことは分かっていませんが、いくつかの説を紹介します。
〇 脳の酸素不足状態の解消
眠くないのにあくびが出る場合は、脳が酸素不足の状態になっている可能性があります。通常、人間の身体は、呼吸によって酸素を取り込みます。しかし、締め切られた部屋や満員電車など、酸素濃度が薄い場所では、充分な酸素を取り込むことができません。すると、脳が酸欠状態に陥り、より多くの酸素を取り込むためにあくびが出ると考えられています。
脳の酸素不足はそれほど珍しくありませんが、長時間続くと頭痛や吐き気などの症状が表れることもあります。酸素不足のときに出るあくびは、身体を守るための生理現象のひとつといえるでしょう。
〇 脳の温度調節
口や鼻から息を吸い込むことで、脳の温度を低下させるためにあくびが出るという説もあります。ストレスや体調不良などで脳の温度が上がったときに、機能障害を防ぐため身体が自然と脳を冷やそうとしているという説です。また、逆に寒いときに出る場合は、口を大きく開けることで頭蓋骨内の血流を促進し、脳の温度を上げるためだとも考えられています。
〇 脳の覚醒の促進
脳の覚醒を促すために、あくびが出るともいわれています。口を大きく開けると頸動脈や頸静脈が圧迫され、脳の覚醒が促されるとする説です。
眠いとき以外にも、疲労や退屈などが原因で頭がぼんやりしているときに、あくびが出たことのある人は多いでしょう。つまり、あまり興味のない話を聞いているときに出るあくびは、脳を覚醒状態に導くためのものともいえます。
〇 あくびの誘発
一説によると、周囲にいる人があくびをすると、自分のあくびも誘発されると考えられています。家族や友人など、親しい相手ほどあくびがうつりやすいという説もありますが、はっきりとしたことは分かっていません。
また、どこからかあくびの声が聞こえてきたり、あくびについて書かれている文章を読んだりするだけでも誘発されるともいわれています。
生あくびは病気のサインの可能性もあるので要注意
生あくびの原因には諸説ありますが、なかには病気の兆候として出ることもあります。例えば、以下のような疾患が当てはまります。
- 脳梗塞
- 脳腫瘍
- 狭心症
- 低血圧
- 睡眠時無呼吸症候群
- 熱中症
- 更年期障害 など
ただし、生あくびだけが症状として出るケースは稀です。手足のしびれやふらつきなどの症状を併発している人は、早めに医師に相談しましょう。
あくびが止まらないときの対処法
眠くないのにあくびが止まらず困ったときは、以下のような方法を試してみましょう。
〇 深呼吸をする
眠くないのにあくびが出る場合は、脳に充分な酸素が行き渡っていない可能性が考えられます。そこで、おすすめの対処法が、深呼吸です。息を大きく吸って、体内に多くの酸素を取り込むよう意識してみましょう。息を大きく吸って、ゆっくり吐くことを繰り返すと、脳の酸欠状態が緩和されやすくなります。
〇 鉄分を摂取する
体内の鉄分が不足すると、酸素を運ぶ役目を持つ「ヘモグロビン」が産生されにくくなり、貧血のリスクが高まります。貧血になると酸素が全身に行き渡りにくくなり、頭痛やめまいなどを引き起こすことがあります。
貧血と、それに伴う酸欠状態を防ぐためにも、普段の食事で鉄分を積極的に摂取しましょう。鉄分は、レバーやアサリ、ほうれん草や小松菜などに多く含まれます。ただし、過剰に摂取するとかえって健康リスクが高まるので注意が必要です。
〇 適度な運動で身体を動かす
仕事やゲームなどで長時間座りっぱなしでいると、血行不良により全身をめぐる酸素量が低下してしまいます。できるだけ長時間同じ姿勢でいることは避け、こまめにストレッチをするなどして身体を動かすようにしましょう。
また、日常的に運動習慣を持つこともおすすめです。ウォーキングやヨガなど、ゆっくりと呼吸をしながらできるような運動が適しています。
〇 病院を受診する
眠くないのにあくびが止まらないときは、思わぬ病気が隠れていることもあります。特に、手足のしびれやめまいなど、あくび以外の症状も表れている場合は速やかに病院を受診しましょう。
あくび以外の症状がない場合でも、日常生活に支障をきたしている場合は、医師による診断を受けることが得策です。
実は睡眠不足に陥っている可能性もある
あくびが止まらない原因はさまざまですが、無自覚な睡眠不足に陥っているケースもあります。
自分の睡眠不足に気付けない人は多いものです。本人は「眠くないのにあくびが出る」と思っていても、実は睡眠不足が原因となっている可能性も考えられます。例えば睡眠時間は充分でも、睡眠の質が低下しているために、身体が睡眠不足の状態に陥っている場合もあります。
あくびが頻発する場合は、睡眠の時間や質に問題がないか振り返ってみることも大切です。
睡眠の質を高めてあくびを防ぐ方法
睡眠習慣を振り返った結果、睡眠不足に陥っていると思われる場合は、まずは充分な睡眠時間を確保したうえで、睡眠の質を高める工夫をしてみましょう。
〇 生活リズムを整える
睡眠の質を高めるためには、規則正しい生活を送ることが大切です。体内時計は朝、太陽の光を浴びるとリセットされるので、起床時間を一定にすることは特に重要です。仕事や家事などで寝る時間が遅くなっても、なるべく毎日同じ時間に起床するよう心がけましょう。
また、朝はタンパク質を多く含む食事をとると、体内リズムが整いやすくなるという説もあります。
〇 就寝の2〜3時間前までに入浴する
私たち人間の身体は、体温が急激に下がると眠気が生じやすくなる仕組みです。お風呂で深部体温が上がったあとに下がると、自然な眠気が生まれます。
入浴のタイミングとしては、就寝の2〜3時間前がおすすめです。ぬるめのお湯にゆっくり浸かれば、リラクゼーション効果も期待できます。
〇 眠りの妨げになる刺激を避ける
就寝前に脳への刺激となるようなことをすると、入眠の妨げとなってしまいます。例えば、コーヒーや緑茶などに含まれるカフェインには覚醒作用があるため、就寝前の摂取は控えた方がよいでしょう。
また、パソコンやスマートフォン、テレビの液晶画面から発せられるブルーライトには、「メラトニン」という睡眠を促すホルモンの分泌を抑える作用があるとされています。できるだけ就寝前1時間以内は、そういったデジタル機器の画面を見過ぎないよう注意しましょう。
〇 寝室環境を整える
睡眠の質は、温度や湿度などの寝室環境による影響も受けます。エアコンの機能を上手に活用して、暑くもなく寒くもない、快適な温度と湿度を保ちましょう。
夏場にエアコンをつけたまま寝ると、夜中に寒くて起きてしまうという場合は、一度低めの温度設定で室温を下げてから、就寝の際に快適な温度まで設定を上げるという方法もあります。
〇 自分に合う枕を使用する
合わない枕を使用していると、肩や首などに負担がかかり、睡眠の質の低下にもつながります。見た目のデザインや価格だけでなく、以下のようなポイントをチェックして自分に合う枕を選びましょう。
- 高さ
- かたさ
- 素材
- サイズ
- 形状
人それぞれ好みやフィット感が異なるので、なるべく実物を試してから購入することをおすすめします。
まとめ
あくび自体のメカニズムははっきりとは解明されていませんが、眠くないときに出るあくび(生あくび)の原因としては、脳の酸欠状態の解消や温度調節などが挙げられます。ただし、人によっては自分の睡眠不足を自覚しておらず、寝不足によるあくびを「眠くないのにあくびが出る」と認識しているケースもあるでしょう。なかには、睡眠時間が足りているのに、睡眠の質の低下により寝不足状態が続いている人もいます。
睡眠の質を向上させるために枕を交換するなら、ぜひ「LOFTY」をご検討ください。LOFTYは、オリンピック公式寝具スポンサーに2期連続で認定された寝具メーカー「エアウィーヴ」のグループ会社です。創業97年の歴史を持ち、累計販売個数は350万個を突破しています。
お近くに店舗がない人も、オンラインショップでなら気軽にご購入いただけます。