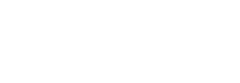大人が寝言をはっきり喋る原因とは?寝言が多くなる原因や対策も解説

寝言は不明瞭なものが大半ですが、なかには起きているときのようにはっきりとした寝言を喋るので、家族に驚かれる人もいるでしょう。寝言がはっきりしていてもそれほど心配する必要はありませんが、場合によっては病気のサインとして表れているケースもあります。本記事では、大人が寝言をはっきり喋る原因と、その対処法を紹介します。
そもそも寝言のメカニズムとは?
寝言(正式には「睡眠時発話」)とは、睡眠中に無意識で発する言葉のことです。実は、寝言のメカニズムは解明されておらず、なぜ睡眠中に言葉を発することがあるのか、はっきりとしたことは分かっていません。
しかし、浅い眠りの段階である「レム睡眠」のときは、夢で話している内容を現実でも発している可能性があると考えられています。
大人が寝言をはっきり喋る原因
睡眠には、浅い眠りの段階の「レム睡眠」と、深い眠りの段階の「ノンレム睡眠」の2種類があります。
一般的に、「レム睡眠」のときははっきりとした寝言が多く、深い眠りの段階である「ノンレム睡眠」のときは不明瞭な寝言が多いとされています。これは、レム睡眠中の寝言は夢に関する内容であり、脳が夢の中で会話している内容をそのまま発話してしまうため、本当に会話をしているような発話が多くなるためです。
一方、ノンレム睡眠中の寝言は不明瞭な言葉が多く、はっきりとした寝言を喋ることは少ないと考えられています。
寝言が多くなる原因
寝言は多くの人が経験するものですが、寝言をよく発する場合は以下のような原因が考えられるでしょう。
日常的なストレス
仕事や人間関係などでストレスを抱えていると、寝言が増える場合があります。特に、寝言の内容に文句や不満が多い場合は、日常生活で自分の気持ちを主張できず、フラストレーションを溜め込んでいる可能性が考えられます。
また、眠りが浅いことで心身の疲れが充分に回復せず、ストレスが蓄積されているケースもあるでしょう。
アルコールやカフェインの摂取
アルコールやカフェインには覚醒作用があり、浅い眠りが増えることで寝言を発しやすくなる場合があります。
カフェインの覚醒作用については広く知られている一方、アルコールの摂取直後は逆に眠気が生じるため、寝るために飲酒をするという人も少なくありません。
しかし、アルコールは摂取後数時間が経過すると、覚醒作用をもたらす「アセトアルデヒド」に分解され、眠りの質が低下する原因になります。また、利尿効果があり、尿意を感じることが多くなるため、中途覚醒が生じやすくなります。
睡眠環境の悪さ
寝室の温度や音など、睡眠環境の影響で眠りが浅くなり、寝言が増えているケースもあります。例えば、以下のような場合は睡眠中に寝苦しさを感じて、眠りが浅くなる可能性が高いでしょう。
- 寝室が暑すぎる・寒すぎる
- 寝室の湿度が高く、ジメジメしている
- 外から聞こえてくる音がうるさすぎる
- 枕やマットレスなどの寝具が身体に合っていない など
不規則な生活
不規則な生活を送っていると、体内時計が乱れやすくなります。その結果、睡眠のリズムが崩れて、寝言の頻度が高くなる場合もあるでしょう。寝る時間・起きる時間だけでなく、食事の時間がバラバラな人も注意が必要です。
遺伝的要因
寝言を発する頻度には、遺伝的要因が関わっているという説もあります。親子ともに寝言が多い場合は、遺伝の可能性があります。ただし、「家族もそうだから大丈夫」と安易に考えず、そのほかの原因はないかしっかりと見極めることが大切です。
はっきり喋る寝言には病気の可能性も隠れている?
はっきりとした寝言は心配のないものがほとんどですが、「毎日のように寝言を発している」「頻繁にうなされている」「睡眠中に怒鳴る、蹴るなどの異常な行動がみられる」といった場合には、思わぬ病気が隠れていることもあります。
睡眠時無呼吸症候群
寝言のほかに、いびきや呼吸停止などの症状がみられる場合は、睡眠時無呼吸症候群が疑われます。
睡眠時無呼吸症候群とは、その名の通り、睡眠中に無呼吸の状態が繰り返される疾患です。中高年に多いとされ、睡眠の質の低下のほか、高血圧や動脈硬化のリスクが高まるともいわれています。
ただし、睡眠時無呼吸症候群では明瞭な寝言はあまり見られず、うめき声やあえぎ声を発するケースが大半です。
レム睡眠行動障害
会話をしているときのようなはっきり喋る寝言のほか、腕を上げる、暴れるなどの激しい動きがみられる場合は、レム睡眠行動障害が疑われます。レム睡眠行動障害とは、夢のなかでの言動が現実世界でもそのまま表れてしまう疾患です。子どもからお年寄りまで幅広い年代が発症し、男性に多いといわれています。
睡眠時てんかん
明瞭な寝言とけいれんのような動きがみられる場合は、睡眠時てんかんの可能性が考えられるでしょう。また、てんかんの発作の開始や終了時に、叫び声やうなり声のような寝言がみられることもあります。そのほか、壁を蹴る、部屋を徘徊するなどの激しい動きも症状のひとつです。
多くの場合、てんかんの発作は数秒から数分間で収まりますが、なかには数時間以上続く場合もあります。
強いストレスによる心の不調
強烈なストレス体験に起因する心の不調から、悪夢にうなされるようになり、はっきりとした寝言が増えるケースもあるでしょう。具体的には、精神的に強いショックを受けた体験によるPTSD(心的外傷後ストレス障害)や不安障害などの可能性が考えられます。心の不調が原因の場合は、不安や恐怖を感じているような寝言や、助けを求める寝言が多くみられます。
このように、寝言の内容やそのほかの行動に気になる点がある場合は、病気のサインの可能性もあるため、医療機関の受診も検討しましょう。
寝言が大きい人に試してほしい対策方法
寝言の大きさや多さに悩んでいる場合は、以下のような対処法を試してみましょう。
ストレスを溜め込みすぎない
ストレスはなるべく溜め込まず、こまめに解消しましょう。アロマや音楽など、自分に合うストレス解消法を見つけることをおすすめします。
また、自分の気持ちを溜め込みがちな人は、相手に思っていることを伝える練習をしましょう。いきなり全て伝えようとすると、かえって精神的負荷がかかる可能性があるので「少しずつ」がポイントです。
適度に運動する
適度な運動は心地よい疲労感をもたらし、スムーズな入眠へとつながります。また、運動はストレス解消にもなるため、無理のない範囲で運動習慣を身につけましょう。ウォーキングやヨガ、ストレッチなど、比較的負荷の少ない運動がおすすめです。
一方、激しい運動はかえって脳を覚醒させてしまうため、就寝前は避けるようにしましょう。
生活リズムを整える
睡眠の質を向上させるためには、生活リズムを整えることが重要です。起床時間と就寝時間をなるべく一定にして、規則正しい生活を心がけましょう。平日に充分な睡眠を取れない場合も、休日の睡眠時間の差はなるべく少なくすることが大切です。
また、就寝前と起床後の行動を整えると、睡眠の質が向上しやすくなります。例えば、就寝前はパソコンやスマートフォンの使用は控える、起床後は太陽の光を浴びるといった習慣を身につけるとよいでしょう。
就寝前の飲酒やカフェインの摂取は避ける
就寝前のアルコールやカフェインの摂取は、睡眠の質を低下させる原因になるため、なるべく控えることをおすすめします。夜間の摂取が適量であれば問題ありませんが、夕食以降は控えるのが望ましいでしょう。
なお、胃腸への負担を軽減するため、夕食は就寝の3〜4時間前までに済ませるとよいとされています。
睡眠環境を整える
睡眠環境の状態は、眠りの質に直結します。冷暖房器具を活用して寝室の温度・湿度を調節し、快適な睡眠環境を保ちましょう。照明をほどよい暗さに調節する、遮音効果のあるカーテンを取り付けるなど、音と光にも注意することが大切です。
また、寝具が合わない場合は、買い換えも検討しましょう。特に、枕は体型や寝姿勢などによって合う・合わないがあります。「自分に合うか」という観点から高さや素材などを比較し、理想的な製品を選ぶことが大切です。
まとめ
はっきりとした寝言はレム睡眠中にみられる傾向があり、多くは夢の内容がそのまま口に出ているものと考えられます。しかし、病気のサインとして表れる場合もあるため、そのほかにも気になる症状がある場合は注意が必要です。
寝言の程度や頻度にお悩みの人には、生活リズムや睡眠環境の見直しをおすすめします。睡眠環境を整えるために枕を買い換えるなら、ぜひLOFTYをご検討ください。
LOFTYは、創業97年の歴史を持つ枕専門店です。オリンピック公式寝具スポンサーに2期連続で認定されたエアウィーヴのグループ会社であり、累計販売個数は350万個を突破しています。