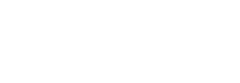寝てる時によだれが出る原因と対策|健康への影響も解説

朝起きると枕によだれがついていたり、電車でうたた寝をした際によだれが垂れて恥ずかしい思いをした経験はありませんか。睡眠中のよだれは単なる生理現象ではなく、健康状態を示すサインでもあります。
本記事では、寝ている時によだれが出る原因から効果的な対策まで詳しく解説していきます。
寝てる時によだれが出る原因
睡眠中によだれが出る現象には複数の要因が関係しており、背景を理解することが対策への第一歩となります。
〇 口呼吸になっている
睡眠中によだれが出る代表的な原因は口呼吸です。本来人間は鼻呼吸が正常な状態であり、鼻毛や線毛、鼻粘膜がホコリや細菌、ウイルスなどの侵入を防ぐフィルターの役割を果たします。しかし口呼吸になると口が開いた状態となり、分泌された唾液がそのまま流れ出てしまいます。
睡眠中も唾液は絶えず分泌されており、無意識のうちに飲み込んでいるのが一般的です。
〇 口や顎の筋力が低下している
口周りや顎の筋力低下も睡眠中のよだれの原因となります。口輪筋と呼ばれる口周りの筋肉が衰えると、口が自然と開きやすくなってしまいます。特に早食いをする人や、食事をしながら他の作業をする人、かたいものをあまり食べない人は筋力が低下しやすい傾向です。
加齢や生活習慣によっても口周りの筋力は低下し、顔全体のゆがみにつながる可能性もあるため注意しましょう。
〇 枕の高さの影響
枕の高さが適切でない場合もよだれが流れやすくなります。よだれは横向きで寝ている時より仰向けで寝ている時の方が垂れにくいものの、枕の高さが合っていないと仰向けの状態をキープすることが困難です。
枕が高い場合は気道がふさがって喉が苦しくなり、枕が低い場合は顎が上がることで首や肩に負担がかかるため、無意識に体勢を変えてしまうことになるでしょう。
〇 アレルギーなどによる鼻づまり
花粉症や風邪の症状により鼻がつまって口呼吸になるケースは多く見られます。普段は正常に鼻呼吸ができていても、鼻炎や鼻づまりの状態では口呼吸になりやすく、これによって喉の乾燥や頭痛を引き起こすおそれもあります。
アレルギー性鼻炎による鼻づまりは長期間続くことがあるため、適切な治療を受けることが必要です。
〇 睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群も口呼吸とよだれの原因となる疾患の1つです。睡眠中は全身の筋肉が緩むため、起きている時よりも気道が狭くなります。舌にふさがれた気道はさらに狭くなり、空気が通りにくくなると酸素を得るため無意識に思い切り息を吸ってしまうことになります。
この状態が続くと睡眠時無呼吸症候群を引き起こし、口呼吸によるよだれの原因となるでしょう。
〇 飲酒の影響
アルコールは筋肉の弛緩を促進し、口周りの筋肉にも影響を与えます。飲酒により口輪筋が緩むと口が開きやすくなり、結果として口呼吸になりよだれが出やすくなります。寝る直前の飲酒をやめることで、寝ている間の筋肉弛緩を最小限に抑えられるため、気道がふさがりにくくなるでしょう。
〇 デジタル機器の影響
現代社会において長時間のスマートフォンやパソコンの使用は、姿勢の悪化を招きます。前傾姿勢が続くと首や顎の位置が変わり、口が開きやすくなる傾向があります。また、デジタル機器の使用により口周りの筋肉を使う機会が減ることも、筋力低下の一因です。
デジタル機器を凝視していると、顔が下向きになり、自然と鼻呼吸の気道が圧迫されるため、口呼吸になりやすい環境を作り出してしまいます。
寝てる時のよだれがもたらす影響
睡眠中のよだれは単なる不快感だけでなく、健康面にもさまざまな悪影響をもたらします。
〇 睡眠の質の低下
口呼吸によるよだれは睡眠の質を著しく低下させる要因となります。口呼吸をしていると効率的な脳の冷却や酸素供給ができなくなるため、脳を充分に休めることができません。また、睡眠中に唾液が口の中に溜まると呼吸がしにくくなり、深い睡眠を妨げます。
〇 免疫力の低下
口呼吸により口内が乾燥すると、唾液の持つ免疫機能が正常に働かなくなります。唾液には細菌やウイルスから身体を守る抗体であるIgA(免疫グロブリンA)が含まれており、これが病原体の体内侵入を防ぐ重要な役割を果たしています。
口呼吸によって唾液が減少すると、このIgAの働きが低下し、身体全体の免疫力が弱くなってしまうでしょう。
〇 細菌・ウイルスへの感染リスクの増加
口呼吸は口内に直接空気が入ってくるため、空気中に含まれるウイルスや細菌が侵入しやすくなります。通常、鼻呼吸では鼻毛や鼻粘膜がフィルターの役割を果たし、有害な物質の侵入を防いでいます。しかし口呼吸ではこのフィルター機能が働かず、また、口内の乾燥を招き、唾液が持つ殺菌作用が低下するため、感染症のリスクが高まります。
特に睡眠中は免疫力が低下しているため、感染リスクがさらに高まります。
〇 口臭の原因となる
睡眠中のよだれが枕に流れ出ることで、口内に残る唾液量が減少してしまいます。口内の唾液不足により細菌が増殖しやすい環境が作られ、口臭の原因となる硫黄化合物が発生しやすくなるでしょう。
特に朝起きた時の口臭が強くなる傾向があり、よだれが多く出た夜ほど翌朝の口臭が気になることが多くなります。
〇 虫歯・歯周病リスクの増加
よだれとして口外に流れ出た唾液は、本来果たすべき口腔保護機能を発揮できません。睡眠中に口内に留まるべき唾液が減少することで、歯の再石灰化作用が低下し、虫歯になりやすい状態が続きます。
また、歯周ポケット内の細菌を洗い流す作用も不充分となり、歯周病の進行リスクが高まる可能性があるでしょう。
寝てる時のよだれの役割
よだれは不快に感じられがちですが、実は口腔健康にとって重要な役割を担っています。
〇 口腔内の洗浄・抗菌
睡眠中の唾液には歯や歯茎についた食べかすを洗い流す浄化作用があります。また、虫歯や歯周病菌などの細菌の増殖を抑える殺菌・抗菌作用もあり、口内環境を清潔に保つ働きをしています。
唾液に含まれるIgAなどの免疫物質は、外から取り込まれる空気に含まれる細菌の侵入を防ぎ、身体の免疫力を高める効果も発揮するでしょう。
〇 口臭を抑える
唾液の洗浄・抗菌作用は口臭を抑えることにも大きく貢献します。口内の細菌バランスを適切に保つことで、口臭の原因となる細菌の繁殖を防ぎます。また、食べかすや細菌を洗い流すことで、口臭の発生源の除去が可能です。
適切な量の唾液が分泌されることで、朝起きた時の口臭も軽減され、口腔内の爽快感を保つことができます。
寝てる時のよだれを防ぐ対策
睡眠中のよだれを防ぐためには、根本的な原因である口呼吸を正す必要があります。
〇 日頃から鼻呼吸を意識する
日中から鼻呼吸を習慣化することが、睡眠中の口呼吸軽減につながります。起きている時に意識的に鼻呼吸を行うことで、睡眠中も自然と鼻呼吸になりやすくなるでしょう。また、口呼吸防止用テープを使用することで、物理的に口を閉じて鼻呼吸を促すことが可能となります。
マスクの着用も効果的で、口周りの湿度を保ち、鼻や口、喉の乾燥を防ぐことができるでしょう。
〇 よく咀嚼して食事をする
食事の際によく咀嚼する習慣をつけることで、口周りの筋肉が刺激され、口呼吸の軽減が見込めます。一口30回程度噛むように意識し、ガムやスルメなどかたいものを食べることも効果的でしょう。長年やわらかいものを食べてきた人は顎の筋肉が低下しているため、意識的に咀嚼回数を増やすことが重要となります。
これにより口輪筋の強化につながり、睡眠中の口の開きを防ぐことが可能となるでしょう。
〇 口周りのトレーニングを取り入れる
口周りの筋肉を鍛える「あいうべ体操」が効果的です。口を楕円に大きく開いて「あ」、口を横に思いっきり開いて「い」、口を前に突き出して「う」、舌をできるだけ突き出して「べ」と発声しましょう。1日3回10セットずつ行うことで、口輪筋の強化が期待できます。
また、舌を上顎に押し当てるような位置に置く習慣をつけることも重要で、正しい舌の位置を意識することが必要でしょう。
〇 医療機関に相談する
睡眠時によだれが出やすい原因が疾患にある際は、医療機関を受診して対処する必要があります。特に鼻づまりが長期間続く場合は、鼻炎・副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、鼻中隔弯曲症などの病気がある場合もあるため、耳鼻科を受診し、適切な治療を受けることが必要です。また、睡眠時無呼吸症候群の疑いがある場合も、専門的な検査と治療が必要でしょう。
〇 枕の見直しをする
適切な枕の高さを選ぶことで、睡眠中の姿勢をただし、よだれを防ぐことができます。低すぎる枕で仰向けに寝ると、自然とあごが上がって口が開き、よだれが出やすくなってしまうでしょう。
横向き寝では鼻呼吸がしやすくなりますが、口の端からよだれが出やすくなるため、横向き寝がしやすいように開発された枕を使用し、口閉じテープを併用することが効果的です。
よだれが治らない場合の注意点
対策を行ってもよだれが軽減しない場合は、より深刻な問題が隠れている可能性があります。
〇 睡眠中に口が開いていないか意識する
睡眠中の口の状態を把握することが対策の第一歩となります。パートナーに確認してもらったり、起床時の口の乾燥具合をチェックしたりすることで、睡眠中の口呼吸の状況を把握できるでしょう。
また、口閉じテープを使用した翌朝の状態を確認することで、テープの効果や口呼吸の程度を判断することが可能です。継続的な観察により、症状の変化や悪化の傾向を把握し、適切な対策を講じることが重要でしょう。
〇 睡眠時以外の唾液過多は疾患の可能性も
日中も含めて唾液の分泌量が異常に多い場合は、唾液過多症などの疾患の可能性があります。唾液過多症は原因が特定されていない病気ですが、消化機能の低下、口内環境の悪化、自律神経の乱れ、妊娠中のホルモンバランスの変化、飲み込む力の低下などが原因として考えられています。
何度も唾液を飲み込まなければならない、会話しづらいなど、日常生活に支障が出る場合は、専門家に相談することが必要でしょう。
まとめ
睡眠中のよだれは口呼吸や筋力低下、枕の高さなどがおもな原因となり、放置すると睡眠の質低下や口腔トラブルを引き起こす可能性があります。対策としては鼻呼吸の習慣化、口周りの筋力強化、適切な枕選びが重要でしょう。
特に枕の見直しは即効性が期待できる対策の1つです。LOFTYは、お客様一人ひとりの体型や好みに合わせた枕を提案するため、計測に基づいた販売方法を確立しています。全国の主要百貨店に店舗を構え、これまでに350万個を超える枕を販売してきた実績は、その品質と信頼性の証でしょう。
睡眠の質を高めるために枕の買い替えを考えているのであれば、LOFTYの枕を一度試してみてはいかがでしょうか。快適な睡眠環境づくりを、LOFTYがサポートします。